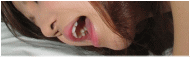大学で声をかけてきた、いつも綺麗だなと思っていた先輩が…2
「ハル、何にする?」
券売機の前でミキちゃんに訊かれて、ボクがハンバーグとスパゲッティのついた日替わり定食のボタンを指差すとミキちゃんは、
「私も」
と言って、二人分の食券を買ってくれた。
向かい合ってテーブルに着くと、当然のことなのだけれどミキちゃんの顔が正面に来て、何だか照れてしまった。
“ねぇ、ミキちゃん、どうしてそんなに人の顔を真っ直ぐに見られるの?”
心の中でそんな風に思ったけど、それでも勇気を出して、できるだけミキちゃんから目を逸らさずにいると、
「ハル、食べないの?」
と言われて慌ててハンバーグを突付いた。
聞いてみると、お父さんの転勤で中学・高校と海外で過ごし、日本の大学に入るためにミキちゃんだけが帰ってきたらしい。
バイクと直接関係するのかどうか分からなかったけれど、何となく普通の女子大生と違うのが合点がいった。
抱きしめられたのも、ハグというやつで他意はなかったらしい。
たったそれだけのことなのに、そうと知ると身分不相応にも何だかがっかりしている自分がいた。
ミキちゃんはもう四年生だったので、就職先として大手会社の内定も貰っていた。
卒業に必要な単位も殆ど揃っていて、残りの学校生活は悠々自適らしい。
身の丈に合っていない学校に偶々受かってしまい、最初から落ちこぼれそうなボクとは大違いだ。
ランチを食べ終わっても午後の間、ボクたちはずっと昔話に花を咲かせていた。
話しているうちに漸くボクも慣れてきて、普通に話ができるようになってきた。
綺麗な人とはしゃべっているだけで楽しい。
日も落ちて周りの学生も少なくなったころ、ボクたちは漸く学食を後にした。
バイクに跨りながらミキちゃんが言った。
「ハル、携帯の番号、言って」
ボクが素直に番号を告げるとミキちゃんはその番号を直接自分の携帯に打ち込むと、ズボンのポケット中のボクの携帯が鳴った。
「じゃあ、またね」
そう言うとミキちゃんは軽くバイクのスロットルを回してエンジンをふかすとメットの裾から伸びた長い髪を風になびかせながら走り去っていった。
ミキちゃんと再会できたのは嬉しかったけれど、三つ上の先輩というのは小学生のときの三つ違いよりも差が大きくて、とんでもなく遠い大人の女性に見えた。
着信をくれたということは電話をしてもいいよ、と言ってくれているのだとは思ったが、何日たってもボクからは連絡できずにいた。
すると、ミキちゃんの方から掛かってきた。
「もしもし、ハル?」
「はい」
「明日、用事ある?」
「いいえ、特に・・・」
「じゃあ、午前十時に中央口の改札で待ってるね」
繁華街のある駅名を一方的に告げられて、ボクの返事を待たずに電話は切れた。
「外国暮らしが長いとこうなのかな?」
そんな風にも思ったけれど、何れにしてもボクはミキちゃんとまた会えるのが嬉しかったので、待ち合わせにだけは遅れないように週末の人出でごった返した駅に向かった。
“こんな人混みの中で会えるのかな”
そんな風に思って、携帯を取り出した。
「待った?」
携帯を弄っていると不意に声を掛けられて、顔を上げるとミキちゃんが目の前に立っていた。
待ち合わせの時間にはまだ少し早かったけど、ミキちゃんも時間の前に来てくれたことが何だか嬉しかった。
「あの、今日は…?」
遠慮がちにボクが尋ねると、ミキちゃんはさも当然のように、
「デートだよ」
と答えた。
少し面食らっているとミキちゃんはボクに腕組みをしてきて、歩き出すようにボクの身体を少し押した。
ミキちゃんの胸の膨らみが二の腕に当たっているのが感じられて、ボクはドキドキしていた。
こうしてミキちゃんとは学校で会うとお茶を飲みながら話をしたり、週末になるとデートに誘ってもらったりした。
ボクはそれだけで幸せな毎日を送っていた。
そんなある日、ボクが風邪を引いて寝込んでいると、ミキちゃんは心配してメールをしてきてくれた。
『ハル、学校に来てないよね?どうしたの?』
『風邪引いちゃいました。』
『熱は?』
『三十九度くらい』
『!!!』
このビックリマークのメールが届いてから約三十分後、ボクの下宿の外で大型のバイクのエンジン音がしたかと思うと、ミキちゃんが部屋に乗り込んできた。
「ちょっとぉ、ハルぅ、風邪なら、どうして連絡くれないの?」
玄関先には、ちょっと怖い顔をしたミキちゃんが立っていた。
「いや、心配するといけないと思って…」
「連絡がないともっと心配するじゃないの!」
ミキちゃんはブーツを脱いで勝手に上り込んできたかと思うとボクの枕元で膝まづいて、ボクのおでこに自分のおでこを当ててきた。
息がかかるほどの距離にミキちゃんの顔があって、それだけで熱が上がりそうだった。
「熱は思ったほどないみたいだけど、何か食べた?」
ボクが首を横に振るとミキちゃんはこれまた勝手に台所に向かうと何の遠慮もなくウチの冷蔵庫の扉を開けた。
「ハル、何にも無いじゃない!」
“うわっ、風邪で臥せっているところへいきなりやってきて冷蔵庫の中身を非難されても…”
とも思ったが、心配してきてくれたのは解っていたので申し訳なさそうに目を伏せるだけに留めておいた。
ミキちゃんはボクのところに戻ってくるとさっき枕元に置いたヴィトンのカバンだけを掴んで出て行った。
寝たままで玄関口の方を見ると、ミキちゃんのブーツが玄関に残ったままだったから、どうやらボクの靴かツッカケでも履いて出て行ったらしい。
二十分経っても、三十分経ってもミキちゃんは帰って来ず、ボクはそのままウトウトと眠ってしまった。
ミキちゃんが持ってきてくれた風邪薬を飲んだせいかもしれない。
目が覚めるとミキちゃんが戻ってきていた。
戻ってきていたのは良いのだけれど、ミキちゃんはボクの隣で無防備に眠っていた。
かぁっと頭に血が上って、心臓がドキドキした。
ミキちゃんは着ていたブラウスとジーンズを脱いで、その辺に置いてあったボクのトレーナーに着替えるとボクと一緒の布団に横たわっていた。
静かな呼吸に合わせて規則正しくミキちゃんの胸が微かに上下している。
それに、とってもいい匂いがした。
足元の方に目をやるとトレーナーの裾から下着がバッチリ見えていて、その先には長い生足が伸びていた。
“タカハル、何をしているんだ!チャンスだぞ!”
大きなフォークを持って先の尖った尻尾をした悪魔がボクの心の中で唆した。
でも、そのころにはもうミキちゃんのことが好きで堪らなかったから、ミキちゃんが目を覚ますのが怖くて何もできなかった。
ボクはただ自分に掛かっていたブランケットの半分をミキちゃんの身体に掛けてあげただけだった。
ミキちゃんは、ボクを弟のように可愛がっているだけで、オスっぽいところを見せたらきっと離れて行ってしまう…。
そんな風に思えて、ボクはミキちゃんを失うことを何よりも恐れていた。
そんな中、薬の所為かボクは再び睡魔に襲われると、ミキちゃんの寝顔を横目に見ながら再び眠ってしまった。
次に目を覚ますと、もうお昼をとっくに回っていた。
隣にミキちゃんの姿はなく、台所に目をやるとミキちゃんが何かを作っているようだった。
どこから持ってきたのかエプロンを着けたミキちゃんの姿が台所にあるのを見ているだけで何だか心が落ち着いた。
よく見ると、さっき横たわっていたままの姿にエプロンをしているだけなので、素足が見えていたりしていて何だかエロい。
「ハル、起きた?」
ボクの視線を感じたのかミキちゃんがボクの方を見て言った。
見つめていたミキちゃんの脚から視線を逸らして、ひと言”うん”とだけ返事した。
「あ、これ、勝手に借りてるね」
ミキちゃんは来ているトレーナーの胸のあたりを少し引っ張って見せた。
ボクは再び”うん”とだけ答えた。
「土鍋もレンゲもないからこんなのでごめんね」
ミキちゃんは普通のお鍋でお粥を作り、スプーンと一緒に枕元に持ってきてくれた。
「こんなのって、お鍋もスプーンもボクのなんですけど…」
そう思ったけど、黙っていた。
ボクは身体を起こして布団の上に座ると、ミキちゃんはお粥をひと匙掬ってフーフーするとボクに食べさせてくれた。
“こんな”お鍋とスプーンだったけど、お粥は間違いなく美味しかった。
食べ終わって少し落ち着いてから周りを見てみると、部屋の中が綺麗に片付いていた。
ミキちゃんが洗濯機を回している間にコソッと押入れを覗いて、秘蔵のエロ本の無事を確認した。
ミキちゃんはそれからもクルクルと良く動いて、あっと言う間に洗濯物を干してくれたりすると、
「早く良くなってね」
そう言って、玄関先でブーツを履くと、胸の前でボクに小さく手を振って帰って行った。
バイクのエンジン音がだんだん小さくなっていくのをボクは耳を凝らしていつまでも聞いていた。
そんなことがあってから、最初のうちは週末だけのお誘いだったのだけれど、そのうち平日にもお誘いを受けるようになった。
食堂でご飯を食べていると、突然目の前に現れて、唐突に言う。
「ねぇ、ハルぅ、いい天気だよねぇ。映画見に行こっかぁ」
“ボクはミキちゃんと違って講義がたくさんあるんですけど…、それに、いいお天気の時は映画じゃないと思うんですけど…”
そう思ったけど、ミキちゃんに、
「ねっ?」
と言われると、何が”ねっ”か分からなかったが、ボクは速攻で頷いていた。
スタスタと前を歩くミキちゃんについていくと、その日もやはり駐車場に向かっていく。
でもその日、ミキちゃんはもうひとつヘルメットを用意していて、ボクにメタルブルーのメットを手渡すと自分で赤い方を被った。
新しいブルーのメットはボクの頭でも大丈夫で、カバンを襷掛けにしてタンデムシートに跨るとミキちゃんに後ろから抱きついた。
「しっかり掴まっていてね」
「はい」
「胸は触っちゃダメだよ」
ミキちゃんがマジで言っているのか冗談で言っているのかが気になったが、バイクが動き出すとそれどころではなくなった。
前の時よりも長いジェットコースターに吐きそうになりながらも必死に耐えて、漸く繁華街に到着したころ、ボクはもうヘロヘロだった。
「ハル、着いたよ」
ミキちゃんに促されてやっとの思いでバイクから降りたのだけど、ボクの腰はもうフラフラだった。
「ほら、ハルったら大げさなんだからぁ」
ミキちゃんに腕組みをされて歩き始めたけど、傍から見ればミキちゃんに連行さられているように見えたかもしれない。
実際にそうだったのだけれど。
その日もミキちゃんは二人分のチケットを買ってくれそうになったのだけれど、
「この間はお世話になったんで、今日はボクが払います」
そう言うと、ミキちゃんは、意外とあっさりと、
「そう?」
とひと言だけ言って、直ぐに財布を引っ込めた。
“うわ、二人分のチケットはちと痛いなぁ…”
そんなことが一瞬脳裏を過るセコいボクだったが、実際に支払ってみるとその日は”映画の日”で約半額だった。
映画は洋画のコメディだったのだけど、ミキちゃんは外国育ちのせいか、字幕が出る半テンポくらい前に笑う。
スクリーンが明るくなった時に光に照らされたミキちゃんの横顔を見ていると、不意にボクの方を向いて、そっと手を伸ばしてきたかと思うと指でこめかみをツンとされて前を向かされた。
その代わり、ミキちゃんはボクの手を取って映画が終わるまでずっと握っていてくれた。
その時点で、ボクはもう映画どころではなくなってしまった。
「お腹空いたね」
映画が終わるとボクたちは近くのイタリアンレストランに入った。
前菜の盛り合わせを二人で分けることにして、それぞれがパスタを一品ずつ選ぶことになったのだけれど、何がいいのかわからない。
「私が好きなの選んじゃっていい?」
ミキちゃんにそう言ってもらった時にはホッとした。
「私は運転があるから飲まないけど、ハルは飲む?」
ボクは首を振りながら、
「まだ、未成年なんで」
と答えると”そうだったね”とひと言呟くと炭酸入りの水を二人分注文してくれた。
この時初めて、味のしない炭酸飲料を口にしたが、いまでは病み付きになっている。
前菜が運ばれてきて、トマトに真っ白なチーズが載ったものを口に運んでいると、ミキちゃんはグリッシーニなる細い木の棒みたいなものをカリカリ齧りながら訊いてきた。
「ねぇ、映画、どうだった?」
ミキちゃんに手を握られてから、後半はあまり見てなかったのだけれど、
「面白かったです」
と応えると、
「どこが?」
と聞かれて、ボクは少し焦った。
でも、嘘を言ってもしようがないと考えて、
「笑うところじゃないですけど、最後のウルウルきたところ」
と答えると、
「ハル、分かってるじゃん、私も!」
そう言ってニッコリ笑うとテーブル越しに手を伸ばして頭を撫ででくれた。
何度かそんなことがあって、ボクはミキちゃんとのデートを存分に楽しませてもらった。
<続く>
続きを読む時に便利です→
・他の体験談も探してみる⇒ FC2 Blog Ranking
[体験告白][エッチ][幼馴染][美人][女子大生]
エッチな体験談
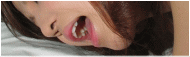
Fc2Blog Ranking|禁断の体験
券売機の前でミキちゃんに訊かれて、ボクがハンバーグとスパゲッティのついた日替わり定食のボタンを指差すとミキちゃんは、
「私も」
と言って、二人分の食券を買ってくれた。
向かい合ってテーブルに着くと、当然のことなのだけれどミキちゃんの顔が正面に来て、何だか照れてしまった。
“ねぇ、ミキちゃん、どうしてそんなに人の顔を真っ直ぐに見られるの?”
心の中でそんな風に思ったけど、それでも勇気を出して、できるだけミキちゃんから目を逸らさずにいると、
「ハル、食べないの?」
と言われて慌ててハンバーグを突付いた。
聞いてみると、お父さんの転勤で中学・高校と海外で過ごし、日本の大学に入るためにミキちゃんだけが帰ってきたらしい。
バイクと直接関係するのかどうか分からなかったけれど、何となく普通の女子大生と違うのが合点がいった。
抱きしめられたのも、ハグというやつで他意はなかったらしい。
たったそれだけのことなのに、そうと知ると身分不相応にも何だかがっかりしている自分がいた。
ミキちゃんはもう四年生だったので、就職先として大手会社の内定も貰っていた。
卒業に必要な単位も殆ど揃っていて、残りの学校生活は悠々自適らしい。
身の丈に合っていない学校に偶々受かってしまい、最初から落ちこぼれそうなボクとは大違いだ。
ランチを食べ終わっても午後の間、ボクたちはずっと昔話に花を咲かせていた。
話しているうちに漸くボクも慣れてきて、普通に話ができるようになってきた。
綺麗な人とはしゃべっているだけで楽しい。
日も落ちて周りの学生も少なくなったころ、ボクたちは漸く学食を後にした。
バイクに跨りながらミキちゃんが言った。
「ハル、携帯の番号、言って」
ボクが素直に番号を告げるとミキちゃんはその番号を直接自分の携帯に打ち込むと、ズボンのポケット中のボクの携帯が鳴った。
「じゃあ、またね」
そう言うとミキちゃんは軽くバイクのスロットルを回してエンジンをふかすとメットの裾から伸びた長い髪を風になびかせながら走り去っていった。
ミキちゃんと再会できたのは嬉しかったけれど、三つ上の先輩というのは小学生のときの三つ違いよりも差が大きくて、とんでもなく遠い大人の女性に見えた。
着信をくれたということは電話をしてもいいよ、と言ってくれているのだとは思ったが、何日たってもボクからは連絡できずにいた。
すると、ミキちゃんの方から掛かってきた。
「もしもし、ハル?」
「はい」
「明日、用事ある?」
「いいえ、特に・・・」
「じゃあ、午前十時に中央口の改札で待ってるね」
繁華街のある駅名を一方的に告げられて、ボクの返事を待たずに電話は切れた。
「外国暮らしが長いとこうなのかな?」
そんな風にも思ったけれど、何れにしてもボクはミキちゃんとまた会えるのが嬉しかったので、待ち合わせにだけは遅れないように週末の人出でごった返した駅に向かった。
“こんな人混みの中で会えるのかな”
そんな風に思って、携帯を取り出した。
「待った?」
携帯を弄っていると不意に声を掛けられて、顔を上げるとミキちゃんが目の前に立っていた。
待ち合わせの時間にはまだ少し早かったけど、ミキちゃんも時間の前に来てくれたことが何だか嬉しかった。
「あの、今日は…?」
遠慮がちにボクが尋ねると、ミキちゃんはさも当然のように、
「デートだよ」
と答えた。
少し面食らっているとミキちゃんはボクに腕組みをしてきて、歩き出すようにボクの身体を少し押した。
ミキちゃんの胸の膨らみが二の腕に当たっているのが感じられて、ボクはドキドキしていた。
こうしてミキちゃんとは学校で会うとお茶を飲みながら話をしたり、週末になるとデートに誘ってもらったりした。
ボクはそれだけで幸せな毎日を送っていた。
そんなある日、ボクが風邪を引いて寝込んでいると、ミキちゃんは心配してメールをしてきてくれた。
『ハル、学校に来てないよね?どうしたの?』
『風邪引いちゃいました。』
『熱は?』
『三十九度くらい』
『!!!』
このビックリマークのメールが届いてから約三十分後、ボクの下宿の外で大型のバイクのエンジン音がしたかと思うと、ミキちゃんが部屋に乗り込んできた。
「ちょっとぉ、ハルぅ、風邪なら、どうして連絡くれないの?」
玄関先には、ちょっと怖い顔をしたミキちゃんが立っていた。
「いや、心配するといけないと思って…」
「連絡がないともっと心配するじゃないの!」
ミキちゃんはブーツを脱いで勝手に上り込んできたかと思うとボクの枕元で膝まづいて、ボクのおでこに自分のおでこを当ててきた。
息がかかるほどの距離にミキちゃんの顔があって、それだけで熱が上がりそうだった。
「熱は思ったほどないみたいだけど、何か食べた?」
ボクが首を横に振るとミキちゃんはこれまた勝手に台所に向かうと何の遠慮もなくウチの冷蔵庫の扉を開けた。
「ハル、何にも無いじゃない!」
“うわっ、風邪で臥せっているところへいきなりやってきて冷蔵庫の中身を非難されても…”
とも思ったが、心配してきてくれたのは解っていたので申し訳なさそうに目を伏せるだけに留めておいた。
ミキちゃんはボクのところに戻ってくるとさっき枕元に置いたヴィトンのカバンだけを掴んで出て行った。
寝たままで玄関口の方を見ると、ミキちゃんのブーツが玄関に残ったままだったから、どうやらボクの靴かツッカケでも履いて出て行ったらしい。
二十分経っても、三十分経ってもミキちゃんは帰って来ず、ボクはそのままウトウトと眠ってしまった。
ミキちゃんが持ってきてくれた風邪薬を飲んだせいかもしれない。
目が覚めるとミキちゃんが戻ってきていた。
戻ってきていたのは良いのだけれど、ミキちゃんはボクの隣で無防備に眠っていた。
かぁっと頭に血が上って、心臓がドキドキした。
ミキちゃんは着ていたブラウスとジーンズを脱いで、その辺に置いてあったボクのトレーナーに着替えるとボクと一緒の布団に横たわっていた。
静かな呼吸に合わせて規則正しくミキちゃんの胸が微かに上下している。
それに、とってもいい匂いがした。
足元の方に目をやるとトレーナーの裾から下着がバッチリ見えていて、その先には長い生足が伸びていた。
“タカハル、何をしているんだ!チャンスだぞ!”
大きなフォークを持って先の尖った尻尾をした悪魔がボクの心の中で唆した。
でも、そのころにはもうミキちゃんのことが好きで堪らなかったから、ミキちゃんが目を覚ますのが怖くて何もできなかった。
ボクはただ自分に掛かっていたブランケットの半分をミキちゃんの身体に掛けてあげただけだった。
ミキちゃんは、ボクを弟のように可愛がっているだけで、オスっぽいところを見せたらきっと離れて行ってしまう…。
そんな風に思えて、ボクはミキちゃんを失うことを何よりも恐れていた。
そんな中、薬の所為かボクは再び睡魔に襲われると、ミキちゃんの寝顔を横目に見ながら再び眠ってしまった。
次に目を覚ますと、もうお昼をとっくに回っていた。
隣にミキちゃんの姿はなく、台所に目をやるとミキちゃんが何かを作っているようだった。
どこから持ってきたのかエプロンを着けたミキちゃんの姿が台所にあるのを見ているだけで何だか心が落ち着いた。
よく見ると、さっき横たわっていたままの姿にエプロンをしているだけなので、素足が見えていたりしていて何だかエロい。
「ハル、起きた?」
ボクの視線を感じたのかミキちゃんがボクの方を見て言った。
見つめていたミキちゃんの脚から視線を逸らして、ひと言”うん”とだけ返事した。
「あ、これ、勝手に借りてるね」
ミキちゃんは来ているトレーナーの胸のあたりを少し引っ張って見せた。
ボクは再び”うん”とだけ答えた。
「土鍋もレンゲもないからこんなのでごめんね」
ミキちゃんは普通のお鍋でお粥を作り、スプーンと一緒に枕元に持ってきてくれた。
「こんなのって、お鍋もスプーンもボクのなんですけど…」
そう思ったけど、黙っていた。
ボクは身体を起こして布団の上に座ると、ミキちゃんはお粥をひと匙掬ってフーフーするとボクに食べさせてくれた。
“こんな”お鍋とスプーンだったけど、お粥は間違いなく美味しかった。
食べ終わって少し落ち着いてから周りを見てみると、部屋の中が綺麗に片付いていた。
ミキちゃんが洗濯機を回している間にコソッと押入れを覗いて、秘蔵のエロ本の無事を確認した。
ミキちゃんはそれからもクルクルと良く動いて、あっと言う間に洗濯物を干してくれたりすると、
「早く良くなってね」
そう言って、玄関先でブーツを履くと、胸の前でボクに小さく手を振って帰って行った。
バイクのエンジン音がだんだん小さくなっていくのをボクは耳を凝らしていつまでも聞いていた。
そんなことがあってから、最初のうちは週末だけのお誘いだったのだけれど、そのうち平日にもお誘いを受けるようになった。
食堂でご飯を食べていると、突然目の前に現れて、唐突に言う。
「ねぇ、ハルぅ、いい天気だよねぇ。映画見に行こっかぁ」
“ボクはミキちゃんと違って講義がたくさんあるんですけど…、それに、いいお天気の時は映画じゃないと思うんですけど…”
そう思ったけど、ミキちゃんに、
「ねっ?」
と言われると、何が”ねっ”か分からなかったが、ボクは速攻で頷いていた。
スタスタと前を歩くミキちゃんについていくと、その日もやはり駐車場に向かっていく。
でもその日、ミキちゃんはもうひとつヘルメットを用意していて、ボクにメタルブルーのメットを手渡すと自分で赤い方を被った。
新しいブルーのメットはボクの頭でも大丈夫で、カバンを襷掛けにしてタンデムシートに跨るとミキちゃんに後ろから抱きついた。
「しっかり掴まっていてね」
「はい」
「胸は触っちゃダメだよ」
ミキちゃんがマジで言っているのか冗談で言っているのかが気になったが、バイクが動き出すとそれどころではなくなった。
前の時よりも長いジェットコースターに吐きそうになりながらも必死に耐えて、漸く繁華街に到着したころ、ボクはもうヘロヘロだった。
「ハル、着いたよ」
ミキちゃんに促されてやっとの思いでバイクから降りたのだけど、ボクの腰はもうフラフラだった。
「ほら、ハルったら大げさなんだからぁ」
ミキちゃんに腕組みをされて歩き始めたけど、傍から見ればミキちゃんに連行さられているように見えたかもしれない。
実際にそうだったのだけれど。
その日もミキちゃんは二人分のチケットを買ってくれそうになったのだけれど、
「この間はお世話になったんで、今日はボクが払います」
そう言うと、ミキちゃんは、意外とあっさりと、
「そう?」
とひと言だけ言って、直ぐに財布を引っ込めた。
“うわ、二人分のチケットはちと痛いなぁ…”
そんなことが一瞬脳裏を過るセコいボクだったが、実際に支払ってみるとその日は”映画の日”で約半額だった。
映画は洋画のコメディだったのだけど、ミキちゃんは外国育ちのせいか、字幕が出る半テンポくらい前に笑う。
スクリーンが明るくなった時に光に照らされたミキちゃんの横顔を見ていると、不意にボクの方を向いて、そっと手を伸ばしてきたかと思うと指でこめかみをツンとされて前を向かされた。
その代わり、ミキちゃんはボクの手を取って映画が終わるまでずっと握っていてくれた。
その時点で、ボクはもう映画どころではなくなってしまった。
「お腹空いたね」
映画が終わるとボクたちは近くのイタリアンレストランに入った。
前菜の盛り合わせを二人で分けることにして、それぞれがパスタを一品ずつ選ぶことになったのだけれど、何がいいのかわからない。
「私が好きなの選んじゃっていい?」
ミキちゃんにそう言ってもらった時にはホッとした。
「私は運転があるから飲まないけど、ハルは飲む?」
ボクは首を振りながら、
「まだ、未成年なんで」
と答えると”そうだったね”とひと言呟くと炭酸入りの水を二人分注文してくれた。
この時初めて、味のしない炭酸飲料を口にしたが、いまでは病み付きになっている。
前菜が運ばれてきて、トマトに真っ白なチーズが載ったものを口に運んでいると、ミキちゃんはグリッシーニなる細い木の棒みたいなものをカリカリ齧りながら訊いてきた。
「ねぇ、映画、どうだった?」
ミキちゃんに手を握られてから、後半はあまり見てなかったのだけれど、
「面白かったです」
と応えると、
「どこが?」
と聞かれて、ボクは少し焦った。
でも、嘘を言ってもしようがないと考えて、
「笑うところじゃないですけど、最後のウルウルきたところ」
と答えると、
「ハル、分かってるじゃん、私も!」
そう言ってニッコリ笑うとテーブル越しに手を伸ばして頭を撫ででくれた。
何度かそんなことがあって、ボクはミキちゃんとのデートを存分に楽しませてもらった。
<続く>
続きを読む時に便利です→
・他の体験談も探してみる⇒ FC2 Blog Ranking
[体験告白][エッチ][幼馴染][美人][女子大生]
- 関連記事
エッチな体験談
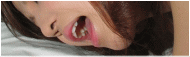
Fc2Blog Ranking|禁断の体験
人気アダルトブログ☆新着情報
コメント
コメントの投稿
トラックバック