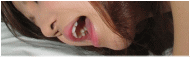忘れていたものを思い出させるような女に出会った体験談 2
私はカーペットに横になり彼女の頭を左腕に乗せ肩を優しく抱いてやった。
「もっと強くぅ」
私はふざけて思い切り抱きしめた。
「くく苦しいぃぃぃ、、、ふぅ~~~。」
力を抜くと彼女が仕返しに抱き返してきた。
そんなことをしながら私達は雨の音を聞きながらしばらく抱きあっていた。
「でも勇二さんって変?」
「なにが?」
「変だよ」
「え?」
「普通さぁ、男の人ってこんな風になったらさぁ胸とか触ったりしない?」
「ああ、そうか」
「私知ってるんだ、男の人って女なら誰でもいいって」
私は今までの彼女の過去を見たような気がした。
それとも言葉の意味を深く読みすぎたのだろうか?
「そんなことない、誰でもいいなんて」
心の中で『また嘘を…』と思ったがあながち嘘でもないと思い直した。
『ほんとうのSEX、お互いの身体が一つになって溶ろけ合うような錯覚って、やっぱ好きな女とじゃないと、、、。ん、いや待てSEXするだけなら出来る、でもテレ下とは出来ん』
「おばさんとは出来ない」
「ふふ、それもそぉか。私はおばさんか」
頭の中で切り替えしを必死に探したが上手い言葉が出てこなかった。
「スキンないし、まぁそういう問題じゃなく」
「彼女さんがいるから?」
『俺がそんなこと気にするか………』
私はまた心の中で私は呟いた。それならSEXくらいしてやっても………とは思わなかったが。
「そんなんじゃなく………」
「うそうそ、解ってるから、勇二さんってそういう人なんだよね」
「おいおい全然解ってないよ」
「でもこうしたら?」
彼女は私のバスローブの胸元を開き胸にキスをしはじめた。
初めは唇をとがらせたた軽いタッチのキスだったが、それに舌先の繊細な動きが加わり、やがてねっとりした舌全体のなめやかな感覚が乳首の周辺を這いまわった。
乳輪に触れたころには私の下半身が敏感に反応はじめてしまった。
彼女の身体から逃れようと力無く抵抗する私のなんと格好悪いこと。
やがて彼女の左手がジーンズの上から股間に触れはじめた。
上から下へ、いきりたった劣情の固まりを包み込むように撫で回わす彼女、その唇は休むことなく私の乳首を吸いつづけていた。
「駄目だよ」
ジーンズのベルトを外そうとする彼女に私は少しだけ強く言った。
「なんで、気持ち良くない?」
「そういう問題じゃなく、駄目なんだよ」
「でもこんなに硬くなってる」
「そりゃそうだけど、、、したくなるでしょ」
「私はいいよ」
そういいながら彼女はチャックを下げジーンズの中に指をすべりこませた。
「なんか濡れてるよ」
パンツの上から彼女が珍棒を握った。
弱すぎず強すぎず、根元から亀頭の先までを彼女の手が優しく撫で回した。
「うふ、硬い…」
「駄目だよ、どうせゴムもないんだから。ゴムがなければHしないんだから、俺は」
私は開き直って言った。
「持ってないの?」
言われてみれば財布の中に入っていたはずだった。でもヤリタイとは思わなかった。まだ頭の中の楔は抜けていなかったようだった。
「そんなの持ってないよ」
「持ってればいいのに。前はあったんだけどなぁ。彼と別れた時に全部捨てちゃった」
「もったいない」
私はふざけた調子で答えた。
私が力なく抵抗を続けていても相変らず彼女は私の股間をまさぐっていた。
すでにパンツの中にまで手が入り込み、肉棒に直接手が触れていた。
「硬いよね」
「そか」私は情けなく笑った。
「イキたいでしょう?」
「そりゃイキたいけど、どうせゴムないし」
「イカせてあげよーか」
彼女の身体が下にずれ落ちていった。
「駄目だよ、駄目」
ジーンズのベルトを器用にはずしパンツを下げようとする彼女に私は本気で抗った。
私の抱いていた彼女に対するイメージをこれ以上壊されたくなかったのかも知れない。
口で奉仕してくれる彼女の姿を私は見たくなかった。
「なんで、駄目なの?」
彼女は身体を起こして言った。
「気持ち良くしてあげたいだけなのに」
彼女は私に背中を向けた。
怒らせてしまったと同時に私は彼女に恥じをかかせてしまったようだ。
私は起き上がり彼女の背中を抱いた。
「こうしているだけでも気持ちいいから」
私はそういいながら彼女の首筋に軽くキスした。
彼女の身体が仰け反った。
未だかつて体験したことのないくらいに敏感な身体の反応だった。
私はもう一度彼女の耳元に軽く唇で触れた。
「あぁぁ~。私それだけで駄目なの…」
彼女が身体を激しくくねらした。
『オモシロイ」
単純に私は思った。
ここまで素直に感じてくれる身体は初めてだった。
図に乗った私は彼女を抱き寄せ首筋からうなじに舌を這わせた。
「はぁぁぁ~あぁ~」
私は彼女の身体に自ら火をつけてしまった。
どれくらい愛撫していただろう。
最後まで達した彼女は汗ばんだ身体を力なく床に横たえていた。
私はまだジーンズをはいたままだった。私はタバコを取り出し火をつけた。
コーヒーカップのふちに乾燥したコーヒーがしみ付いていた。
「なんか、、、ごめんなさい」
彼女がようやく口を開いた。
「恥ずかしい」
「そんなことないよ素直なだけじゃん」
「でも私だけ………」
「あぁ、そんなこと気にしないでいいから。どーせゴムもないんだし」
「ゴムしなくても平気だよ」
「看護婦さんがなに言ってるの?安全日なんてあると思ってちゃ駄目だよ」
「じゃなくて、私できるから」
「うん?」
「私できるよ」
そういって彼女は私の身体の上に跨ってきた。
「駄目だよ、どうせ口じゃイケないから」
「大丈夫、自信あるから」
私は一抹の寂しさを感じた。それと同時に彼女に身を委ねてしまえ、という投げやりな感情が私の楔を完全に抜き取った。
彼女の舌先が肉棒に触れた。そしてゆっくりと彼女の口の中に肉棒が飲まれていった。
生温かな感触が亀頭にまとわりつく。
彼女の口の中を出入りする肉棒がいやらしく濡れていた。
長い時間ひたすら彼女は口での奉仕を続けてくれた。
それでも肉棒は硬さを衰えぬままいきり立ったままだった。
やがて彼女は肉棒を含むのをやめた。
「駄目だぁ」
彼女が諦めたように言った。
「自信なくした、ねぇどうしたらイケるの?教えて」
「解らない」
彼女にテクニックがなかったわけではない。ただ舌が滑らかすぎるだけだ。
「なんか悲しいな。私だけ気持ち良くしてもらって…」
「気にしないでいいよ。フェラチオじゃ駄目なんだ」
「じゃ入れればイケるの?」
「そりゃそうだ。入れてもイケなかったら困る」
私は笑いながら言った。
もう終りにするかしないかなんて、どうでも良かった。
「じゃあ入れる」
そう言うと彼女は起き上がって私の身体に跨り、肉棒に手を添え身体の中に器用に導いた。
「はあぁぁぁ~」
腰を落としながら彼女は妙な喘ぎ声をあげた。
ズブズブと彼女の身体の中に私の肉棒がめり込んでいった。
「入ってる、入ってる」
彼女が腰を前後に振りはじめた。
「あぁぁぁ~、あぁ気持ちヨ、いぃぃぃ」
先ほどの指での愛撫とはまた違った反応に私は少し驚いた。やはり肉棒と指では違うのだと改めて認識した。
彼女の愛液が肉棒から睾丸につたっていた。
彼女は自分のクリトリスを私の恥骨にあてるように激しく強く、腰を振りつづけた。
正直フェラチオよりもイケそうな気配はなかった。前後の動きで気持ちの良い男はいるのだろうか?
それを彼女も知っていた。
「これじゃイケないんだよね。男の人は気持ち良くないんだよね」
そう言って彼女はしゃがむような姿勢になって腰を上下に動かしはじめた。
「あぁぁ、、、当たってるぅ、当たってるの解るぅ?」
「解るよ」
私は彼女の淫乱さに正直驚いていた。
形の良い乳房がリズムにあわせるかのように揺れていた。
身体をそらせて一心に腰を振る女の魔性の姿に、私は女の業を見たような気がした。
それは私の背負った業よりも深く思えた。
「駄目ぇ?駄目ぇ?気持ち良くならない?」
彼女が私に訴えかけるような艶めかしい目で言った。
眉間にしわを寄せ、身体の歓びを我慢するかのようなその妖しい表情だけでも私はイケるような気がした。
「ああ、気持ちいいよ。でも中に出せないから」
「いいの、いいの、私の中にいっぱい出して。ねぇ早く出して」
「駄目駄目。そんなの駄目」
彼女が腰の動きを止めた。
「早く出してくれないとぉ、私だめになっちゃうの。」
息を切らしながら彼女が言った。
「なんで?」
「うんとねぇ、あーん恥ずかしいぃ」
「何よ?」
私達は一つに繋がったまま話していた。
「笑わない?」
「笑わないよ」
「あのねぇ、、、おしっこしたくなっちゃうの、、、。だって膣のコッチ側って膀胱なんだよ」
急に看護婦さんになった彼女は自分の陰毛のあたりを指差した。
「へー言われてみればそうだ」
私は起き上がり彼女を寝かせた。
そして彼女の太股を大きく広げて股間と股間を合わせた。
彼女が手を伸ばし肉棒を掴んだ、膣に導こうとしているのだ。
「なに、この手は?」
「え?は?」
彼女の条件反射のようだった。
恥ずかしそうに照れている彼女の眉間にまたしわがよった。
「あああぁぁぁ~~~。ねぇ、はやくイッテね、もう私だめだから、はぁぁ~~~」
はやくイッテと言う割には充分に彼女は膣の中で感じていた。
肉棒を左右にかき回すと声が変わる。
乳房を鷲掴みにするとまた違った声を上げる、乳首をつまむとまた違った声をあげる、、、『オモシロすぎる』私は思った。
「ねぇねぇ、私はもういいからハヤクぅぅぅ」
そうだ、ゴムなしの生だったんだ、カウパー氏腺液が漏れてるぞぉ、そう思った私は自分の快感の為だけに彼女の膣の中を掻き回した。
そして彼女の喘ぎ声が大きく伸び続けた瞬間に彼女の下腹部の上に劣情だけじゃないはずの白濁とした精液をまき散らした。
「気持ち良かった?」
まだ少し息の荒い声で彼女が言った。
「ああ、すごく気持ち良かったよ」
「うふ、嬉しい。私も気持ち良かった。また気持ち良くしてね」
彼女は甘えた声を出した。
「ゴムがあればね、用意しといてね」
「えー私が買うの?」
「ゴムがなければ、、、」
「したくせに」彼女が笑いながら言った。
「不覚………」
窓の外で鳥の鳴き声がしていた。もう夜といえる時間ではなかった。
「こんな時間か」
「ごめんね、ごめんね、私は休みなのにごめんね。早く帰って、彼女さん心配してる」
しきりに謝る彼女に逆に追い立てられるように私は女子寮を出た。
雨は上がっていた。青みを帯びてきている空に雲は見当たらなかった。
身体にはだるさを感じていても眠くはなかった、頭は不思議と冴えていた。
「俺は何をしにいったのだろうか、した行為はいつもと同じ、、、。でも、、、でも何かいつもと違う」
高速道路を走らせていると携帯に着信があった。
「雨あがっててよかったね。気を付けて帰ってね」
「ああ、ありがと」
「それとぉ、、、。また、、、逢えるよね」
「ああ」
視線をそらすと川をはさんで街が見渡せた。空は夏の空だった。
今年の夏は突然に訪れたようだった。
・他の体験談も探してみる⇒ FC2 Blog Ranking
[体験告白][エッチ][愛撫][乳首舐め][手コキ][手マン][フェラチオ][生挿入][騎乗位][セックス]
エッチな体験談
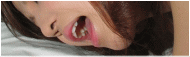
Fc2Blog Ranking|禁断の体験
「もっと強くぅ」
私はふざけて思い切り抱きしめた。
「くく苦しいぃぃぃ、、、ふぅ~~~。」
力を抜くと彼女が仕返しに抱き返してきた。
そんなことをしながら私達は雨の音を聞きながらしばらく抱きあっていた。
「でも勇二さんって変?」
「なにが?」
「変だよ」
「え?」
「普通さぁ、男の人ってこんな風になったらさぁ胸とか触ったりしない?」
「ああ、そうか」
「私知ってるんだ、男の人って女なら誰でもいいって」
私は今までの彼女の過去を見たような気がした。
それとも言葉の意味を深く読みすぎたのだろうか?
「そんなことない、誰でもいいなんて」
心の中で『また嘘を…』と思ったがあながち嘘でもないと思い直した。
『ほんとうのSEX、お互いの身体が一つになって溶ろけ合うような錯覚って、やっぱ好きな女とじゃないと、、、。ん、いや待てSEXするだけなら出来る、でもテレ下とは出来ん』
「おばさんとは出来ない」
「ふふ、それもそぉか。私はおばさんか」
頭の中で切り替えしを必死に探したが上手い言葉が出てこなかった。
「スキンないし、まぁそういう問題じゃなく」
「彼女さんがいるから?」
『俺がそんなこと気にするか………』
私はまた心の中で私は呟いた。それならSEXくらいしてやっても………とは思わなかったが。
「そんなんじゃなく………」
「うそうそ、解ってるから、勇二さんってそういう人なんだよね」
「おいおい全然解ってないよ」
「でもこうしたら?」
彼女は私のバスローブの胸元を開き胸にキスをしはじめた。
初めは唇をとがらせたた軽いタッチのキスだったが、それに舌先の繊細な動きが加わり、やがてねっとりした舌全体のなめやかな感覚が乳首の周辺を這いまわった。
乳輪に触れたころには私の下半身が敏感に反応はじめてしまった。
彼女の身体から逃れようと力無く抵抗する私のなんと格好悪いこと。
やがて彼女の左手がジーンズの上から股間に触れはじめた。
上から下へ、いきりたった劣情の固まりを包み込むように撫で回わす彼女、その唇は休むことなく私の乳首を吸いつづけていた。
「駄目だよ」
ジーンズのベルトを外そうとする彼女に私は少しだけ強く言った。
「なんで、気持ち良くない?」
「そういう問題じゃなく、駄目なんだよ」
「でもこんなに硬くなってる」
「そりゃそうだけど、、、したくなるでしょ」
「私はいいよ」
そういいながら彼女はチャックを下げジーンズの中に指をすべりこませた。
「なんか濡れてるよ」
パンツの上から彼女が珍棒を握った。
弱すぎず強すぎず、根元から亀頭の先までを彼女の手が優しく撫で回した。
「うふ、硬い…」
「駄目だよ、どうせゴムもないんだから。ゴムがなければHしないんだから、俺は」
私は開き直って言った。
「持ってないの?」
言われてみれば財布の中に入っていたはずだった。でもヤリタイとは思わなかった。まだ頭の中の楔は抜けていなかったようだった。
「そんなの持ってないよ」
「持ってればいいのに。前はあったんだけどなぁ。彼と別れた時に全部捨てちゃった」
「もったいない」
私はふざけた調子で答えた。
私が力なく抵抗を続けていても相変らず彼女は私の股間をまさぐっていた。
すでにパンツの中にまで手が入り込み、肉棒に直接手が触れていた。
「硬いよね」
「そか」私は情けなく笑った。
「イキたいでしょう?」
「そりゃイキたいけど、どうせゴムないし」
「イカせてあげよーか」
彼女の身体が下にずれ落ちていった。
「駄目だよ、駄目」
ジーンズのベルトを器用にはずしパンツを下げようとする彼女に私は本気で抗った。
私の抱いていた彼女に対するイメージをこれ以上壊されたくなかったのかも知れない。
口で奉仕してくれる彼女の姿を私は見たくなかった。
「なんで、駄目なの?」
彼女は身体を起こして言った。
「気持ち良くしてあげたいだけなのに」
彼女は私に背中を向けた。
怒らせてしまったと同時に私は彼女に恥じをかかせてしまったようだ。
私は起き上がり彼女の背中を抱いた。
「こうしているだけでも気持ちいいから」
私はそういいながら彼女の首筋に軽くキスした。
彼女の身体が仰け反った。
未だかつて体験したことのないくらいに敏感な身体の反応だった。
私はもう一度彼女の耳元に軽く唇で触れた。
「あぁぁ~。私それだけで駄目なの…」
彼女が身体を激しくくねらした。
『オモシロイ」
単純に私は思った。
ここまで素直に感じてくれる身体は初めてだった。
図に乗った私は彼女を抱き寄せ首筋からうなじに舌を這わせた。
「はぁぁぁ~あぁ~」
私は彼女の身体に自ら火をつけてしまった。
どれくらい愛撫していただろう。
最後まで達した彼女は汗ばんだ身体を力なく床に横たえていた。
私はまだジーンズをはいたままだった。私はタバコを取り出し火をつけた。
コーヒーカップのふちに乾燥したコーヒーがしみ付いていた。
「なんか、、、ごめんなさい」
彼女がようやく口を開いた。
「恥ずかしい」
「そんなことないよ素直なだけじゃん」
「でも私だけ………」
「あぁ、そんなこと気にしないでいいから。どーせゴムもないんだし」
「ゴムしなくても平気だよ」
「看護婦さんがなに言ってるの?安全日なんてあると思ってちゃ駄目だよ」
「じゃなくて、私できるから」
「うん?」
「私できるよ」
そういって彼女は私の身体の上に跨ってきた。
「駄目だよ、どうせ口じゃイケないから」
「大丈夫、自信あるから」
私は一抹の寂しさを感じた。それと同時に彼女に身を委ねてしまえ、という投げやりな感情が私の楔を完全に抜き取った。
彼女の舌先が肉棒に触れた。そしてゆっくりと彼女の口の中に肉棒が飲まれていった。
生温かな感触が亀頭にまとわりつく。
彼女の口の中を出入りする肉棒がいやらしく濡れていた。
長い時間ひたすら彼女は口での奉仕を続けてくれた。
それでも肉棒は硬さを衰えぬままいきり立ったままだった。
やがて彼女は肉棒を含むのをやめた。
「駄目だぁ」
彼女が諦めたように言った。
「自信なくした、ねぇどうしたらイケるの?教えて」
「解らない」
彼女にテクニックがなかったわけではない。ただ舌が滑らかすぎるだけだ。
「なんか悲しいな。私だけ気持ち良くしてもらって…」
「気にしないでいいよ。フェラチオじゃ駄目なんだ」
「じゃ入れればイケるの?」
「そりゃそうだ。入れてもイケなかったら困る」
私は笑いながら言った。
もう終りにするかしないかなんて、どうでも良かった。
「じゃあ入れる」
そう言うと彼女は起き上がって私の身体に跨り、肉棒に手を添え身体の中に器用に導いた。
「はあぁぁぁ~」
腰を落としながら彼女は妙な喘ぎ声をあげた。
ズブズブと彼女の身体の中に私の肉棒がめり込んでいった。
「入ってる、入ってる」
彼女が腰を前後に振りはじめた。
「あぁぁぁ~、あぁ気持ちヨ、いぃぃぃ」
先ほどの指での愛撫とはまた違った反応に私は少し驚いた。やはり肉棒と指では違うのだと改めて認識した。
彼女の愛液が肉棒から睾丸につたっていた。
彼女は自分のクリトリスを私の恥骨にあてるように激しく強く、腰を振りつづけた。
正直フェラチオよりもイケそうな気配はなかった。前後の動きで気持ちの良い男はいるのだろうか?
それを彼女も知っていた。
「これじゃイケないんだよね。男の人は気持ち良くないんだよね」
そう言って彼女はしゃがむような姿勢になって腰を上下に動かしはじめた。
「あぁぁ、、、当たってるぅ、当たってるの解るぅ?」
「解るよ」
私は彼女の淫乱さに正直驚いていた。
形の良い乳房がリズムにあわせるかのように揺れていた。
身体をそらせて一心に腰を振る女の魔性の姿に、私は女の業を見たような気がした。
それは私の背負った業よりも深く思えた。
「駄目ぇ?駄目ぇ?気持ち良くならない?」
彼女が私に訴えかけるような艶めかしい目で言った。
眉間にしわを寄せ、身体の歓びを我慢するかのようなその妖しい表情だけでも私はイケるような気がした。
「ああ、気持ちいいよ。でも中に出せないから」
「いいの、いいの、私の中にいっぱい出して。ねぇ早く出して」
「駄目駄目。そんなの駄目」
彼女が腰の動きを止めた。
「早く出してくれないとぉ、私だめになっちゃうの。」
息を切らしながら彼女が言った。
「なんで?」
「うんとねぇ、あーん恥ずかしいぃ」
「何よ?」
私達は一つに繋がったまま話していた。
「笑わない?」
「笑わないよ」
「あのねぇ、、、おしっこしたくなっちゃうの、、、。だって膣のコッチ側って膀胱なんだよ」
急に看護婦さんになった彼女は自分の陰毛のあたりを指差した。
「へー言われてみればそうだ」
私は起き上がり彼女を寝かせた。
そして彼女の太股を大きく広げて股間と股間を合わせた。
彼女が手を伸ばし肉棒を掴んだ、膣に導こうとしているのだ。
「なに、この手は?」
「え?は?」
彼女の条件反射のようだった。
恥ずかしそうに照れている彼女の眉間にまたしわがよった。
「あああぁぁぁ~~~。ねぇ、はやくイッテね、もう私だめだから、はぁぁ~~~」
はやくイッテと言う割には充分に彼女は膣の中で感じていた。
肉棒を左右にかき回すと声が変わる。
乳房を鷲掴みにするとまた違った声を上げる、乳首をつまむとまた違った声をあげる、、、『オモシロすぎる』私は思った。
「ねぇねぇ、私はもういいからハヤクぅぅぅ」
そうだ、ゴムなしの生だったんだ、カウパー氏腺液が漏れてるぞぉ、そう思った私は自分の快感の為だけに彼女の膣の中を掻き回した。
そして彼女の喘ぎ声が大きく伸び続けた瞬間に彼女の下腹部の上に劣情だけじゃないはずの白濁とした精液をまき散らした。
「気持ち良かった?」
まだ少し息の荒い声で彼女が言った。
「ああ、すごく気持ち良かったよ」
「うふ、嬉しい。私も気持ち良かった。また気持ち良くしてね」
彼女は甘えた声を出した。
「ゴムがあればね、用意しといてね」
「えー私が買うの?」
「ゴムがなければ、、、」
「したくせに」彼女が笑いながら言った。
「不覚………」
窓の外で鳥の鳴き声がしていた。もう夜といえる時間ではなかった。
「こんな時間か」
「ごめんね、ごめんね、私は休みなのにごめんね。早く帰って、彼女さん心配してる」
しきりに謝る彼女に逆に追い立てられるように私は女子寮を出た。
雨は上がっていた。青みを帯びてきている空に雲は見当たらなかった。
身体にはだるさを感じていても眠くはなかった、頭は不思議と冴えていた。
「俺は何をしにいったのだろうか、した行為はいつもと同じ、、、。でも、、、でも何かいつもと違う」
高速道路を走らせていると携帯に着信があった。
「雨あがっててよかったね。気を付けて帰ってね」
「ああ、ありがと」
「それとぉ、、、。また、、、逢えるよね」
「ああ」
視線をそらすと川をはさんで街が見渡せた。空は夏の空だった。
今年の夏は突然に訪れたようだった。
・他の体験談も探してみる⇒ FC2 Blog Ranking
[体験告白][エッチ][愛撫][乳首舐め][手コキ][手マン][フェラチオ][生挿入][騎乗位][セックス]
- 関連記事
エッチな体験談
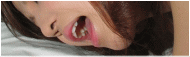
Fc2Blog Ranking|禁断の体験
人気アダルトブログ☆新着情報
コメント
コメントの投稿
トラックバック